こんにちは
管理者 とも@生き方カウンセラーです
子供の頃、「人を好きになるってどういうこと?」「愛と恋って、どう違うの?」などを友達と話した経験って、あったのではないでしょうか
私は、子供の頃だけでなく、大人になっても「人を愛することって???」と考え込むことが何度もありました
この疑問に対して、 Erich Fromm (以下、Erich Frommを「Formm」とします) 著「愛するということ」を読むことで、

あー、「愛する」ってこういうことかも
となるかもしれません
そこで、今回はこの本を参照に、「愛するということ」について、考えてみたいと思います
人を「愛する」ようになるための3つの方法
1 「愛する」とは技術である、ということを知る
2 愛の理論(愛は何よりも与えることであり、もらうことではない)を知る
3 愛の修練を行う
1 「愛する」とは、技術である
「愛してる」
っていう言葉から、イメージするものとして
YOASOBIの「アイドル」 (左をクリックするといきなり歌が流れます)という曲です
「愛」という言葉
これを言葉にしたとき、
それが本物の「愛」なのか
「愛してる」って言ってしまったけど、それは嘘だったんじゃないか
などと心配になり、
余計に「愛する」って何だろう、どんなことなんだろう
と悩んでしまう
こんなことを、若い頃から繰り返してきました
だから、「愛している」と言う場面では、自分の心の中で
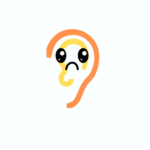
今のこの気持ちが、「愛している」っていう感情なんだー
と、言い聞かせていたことがよくありました
そんな自分でも、唯一自信を持って「愛している」と心から言えるのは、
自分の子供のこと
でした
そんな想いを持っていて、YOASOBIのこの曲を知り、さらに、この曲が主題歌となった「推しの子」を読んでみました
なんか、とても共感できる内容でした
この「愛する」と言うことに関して私が思ってきたことは、「推しの子」の第1話から第9話を読んでいただけると、わかりやすいと思います
こんな私ですが、Frommの「愛するということ」を読んだ時に、
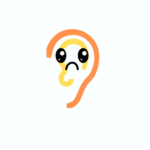
自分が考えていた「愛するといこと」は間違っていたんだー
と思いました
それは、まずこの本のタイトル「愛するということ」ですが、英語のタイトルでは「THE ART OF LOVING」となっています
この本文では、「愛は技術である」としています
この記事を読んでくれている方々は、この「愛は技術である」ということを聞いて、どのようなことを考えますか
私がこれを見た時に、

本を読むまで、この英語タイトルに気づかなかった
と、何も言えなくなったくらいびっくりしました
というのも、

「愛」って感情であり、ドキドキしたり、大切に思う気持ちのことだよねー
って、思っていたもので・・・
この本を読み始めると、私の「愛」という考え方が、全く違っていたということに、さらに驚かされました
Frommは
「愛について学ばなければならないことがあるのだと考えている人はほとんどいない」
としています
また、Frommは、このような「奇妙な態度(『愛について学ばなければならないことがあることを考えない態度』のこと」)の前提として、
①たいていの人は愛の問題を、「愛するという問題」、「愛する能力の問題」としてではなく、「愛されるという問題」としての捉え
→人びとにとって重要なのは、どうすれば愛されるか、どうすれば愛される人間になるか、ということ
②愛の問題とはすなわち「対象の問題」であって「能力の問題」ではない、という思い込み
→「愛することは簡単」だが、「愛するにふさわしい相手」、あるいは「愛されるにふさわしい相手」を見つけることは難しい、という考え
③恋に「落ちる」という最初の体験と、「愛している」あるいは、「愛の中にとどまっている」という持続的な状態とを、混同していること
→最初は二人ともそんなこと(不意に親しくなる奇跡は、親しくなるにつれ、親密さから奇跡めいたところがなくなり、やがて反感、失望、倦怠が最初のなごりを消し去ってしまうこと)は夢にも思わず、たがいに夢中になった状態、頭に血がのぼった状態を、愛の強さと思いこむ
→じつはそれは、それまで二人がどれほど孤独であったかを示しているにすぎないかもしれないということ
を示しています
さらに、「愛の失敗(人を愛せなかったこと)を克服する方法」として、適切な方法は1つしかなく、
「失敗の原因を調べ、そこから進んで愛の意味を学ぶこと」
としています
そのための第一歩として
「愛は技術であると知ること」
→どうすれば人を愛せるようになるかを学びたければ、他の技術、例えば音楽、絵画、大工仕事、医学、工学などの技術を学ぶときと同じ道をたどらなければならない
であり、どんな技術でも習得する際に踏まなければならない3つの過程として
①理論に精通すること
②その修練に励むこと
③その技術を習得することが自分にとっての究極の関心事にならなければならない、ということ
を示しています
2 愛の理論(愛は何よりも与えることであり、もらうことではない)を知る
Frommは、「人間のもっとも強い欲求」として
「孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいという欲求」
を示しています
この欲求に応えるために、人は
・自然と一体になる(動物の仮面を被る、祝祭的興奮状態を作る)
・集団に同調する、仕事も娯楽も型通りのものになっている
・創造的活動をする
これらの活動は、一時的であったり、偽りであったり、人間同士の一体感でなかったりする
(孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいという欲求に応えるための)完全な答えは、
人間どうしの一体化、他者との融合、すなわち「愛」にある
としています

えーと
つまり
孤独にならないための方法として、
・自然と1つになる→一時的には孤独にならない
・周囲の人々への同調→偽りの一体感
・創造的活動→働く者とその対象(人ではない物)が一体となる
から、孤独にならない方法としては、ダメということなの?

そうですね
Frommは、
「孤立しているという意識から不安が生まれる」
としています
その不安をなくす方法として、人々は、古今東西、様々なことをしてきています
しかし、それらの多くは、上に挙げた3つのことをしており、失敗しています
そこで、孤独から抜け出す方法として「愛」を示しています
Frommは
「愛は能動的な活動であり、受動的な感情ではない」
「その中に『落ちる』ものではなく、『みずから踏みこむ』ものである」
としています
そして、「愛」の能動的性質の要素の1つとして
「愛は何よりも与えることであり、もらうことではない」
と言っています

Frommは、
愛は感情ではなく、能動的な活動
としていることに驚かされました
能動的な活動としての「与える」とは、
自分自身を、自分のいちばん大切なものを、自分の生命を与えること
→自分の喜び、興味、理解、知識、ユーモア、悲しみなど、自分のなかに息づいているもののあらゆる表現を与えること
その結果
人は他人を豊かにし、自分自身の生命感を高めることによって、他人の生命感を高める
→与えることによって、かならず他人のなかに何かが生まれ、その生まれたものは自分にはね返ってくる
つまり
「与える」ということは、「他人をも与える者にする」ということであり、たがいに相手のなかに芽ばえさせたものから得る喜びを分かちあう
=愛とは愛を生む力
と、Frommは示しています
さらに、Frommは「愛」の能動的性質の要素として、
⚪︎配慮:愛とは、愛する者の生命と成長を積極的に気にかけること
⚪︎責任:「責任がある」ということは、他人の要求に応じられる、応じる用意がある、という意味
⚪︎尊重:他人がその人らしく成長発展してゆくように気づかうこと
⚪︎知:自分自身に対する関心を超越して、相手の立場にたってその人を見ることができたときにはじめて、その人を知ることができる→自分自身を与え、相手のうちへと入ってゆく行為において、私は自分自身を、相手と自分の双方を、人間を、発見する(知る)
とし、これらは依存しあっているのですが、詳細は本書をご覧ください
では、このような技術である「愛するということ」を身につけるためには、どうしたらいいのでしょうか
それは、「修練」です

何かの技術の修練について学ぼうというとき、その修練を積む以外に方法はない、とFrommは示しています
確かに、技術を身につけるためには、何度も何度も繰り返し挑戦して、自分の持っている技術を鍛えて成長させていかないといけないようには思えます
では、どんな修練をするといいのですかねぇ
3 愛の修練を行う
Frommは、愛の修練の要素について、次の4つを挙げています
(1)技術の修練には規律が必要である
(2)集中が技術の習得にとって必要条件である
(3)何かを達成するためには忍耐が必要である
(4)技術の習得に最高の関心を抱くことも、技術を身につけるための必要条件の1つである
(5)愛の技術の修練には、「信じる」ことの修練が必要である
これらについて、みていきます
(1)技術の修練には規律が必要である
「規律」とは、デジタル大辞泉によると
1 人の行為の基準として定められたもの。おきて。「―を守る」
2 一定の秩序。「―正しい生活」
としています
Frommは、
「規律正しくやらなければ、どんなことでも絶対に上達しない」
「『気分が乗っている』ときにだけやるのでは、楽しい趣味になりうるかもしれないが、そんなやり方では絶対にその技術を習得することはできない」
と示します
また、この規律に関して重要なこととして
「外から押しつけられた規則か何かのように規律の修練を積むのはなく、規律が自分自身の意思の表現となり、楽しいと感じられ、ある種の行動にすこしずつ慣れてゆき、ついにそれをやめると物足りなく感じられるようになること」
としています

例えば、
「毎日、成長ができるように声をかけていく」
と決めたら、必ずやるっていうことと思います

なんか、運動に似ていますねぇ
運動も毎日続けていると、やめるともったい無いというか、手持ちぶたさになりますよねぇ

そうですね
運動も、その種目の能力を高めたいという思いで行う「修練」の1つですからねぇ
「規律」が「守らなければいけないもの」から「守りたいもの」に変わるっていうんですかねぇ

でもさぁ、この「規律を守る」と「愛する」ことが、どうも結びつかないんだよねぇ

うん、うん
そう思う
この2つにどんな関係があるんだろう?

なるほど
2人とも、この2つのつながりがよくわからないっていう状況なんですねぇ
そうですねぇ、この規律だけが「愛の修練の要素」ではないので、他の要素も考えていくとわかってくるかもしれません
次の要素を考えてみましょう
規律正しく行なっていくことよりもはるかに難しいのが、集中力を身につけることです
(2)集中が技術の習得にとって必要条件である
Frommがあげる一番重要なステップとして、本も読まず、ラジオも聞かず、タバコも吸わず、酒も飲まずに、一人でじっとしていられるようになることをあげています
つまり
集中できる=一人でじっとしていられるようになること
→愛することができるようになるための1つの必須条件
というのも、
自分の足で立てないという理由で、誰か他人にしがみつくとしたら、その相手は命の恩人にはなりうるかもしれないが、2人の関係は愛の関係ではない

このような関係は、助け合いではなく、依存し合いとなってしまうのでしょう
例えば「推しの子」第97話の中のセリフで
「自立した人間二人が寄り添う事に意味があるの」「そうじゃない関係はただの依存だから」
というものがありました
自分一人で考え、行動することができる2人が愛し合うことで、より思考が深まり、人生が豊かになっていくのだと思います
また、Frommは
一人でいる努力をしていると、そわそわと落ち着かなくなり、かなりの不安を覚えたりして、この努力が何の価値もない、ばかばかしい、時間をとられすぎる、などと理屈をつけて、この修練を続けたくないという自分の気持ちを正当化しようとする
とし、さらに、
他人との関係において精神を集中させるということは、何よりもまず、相手の話を聞くこと
と示しています
そして、
いま何かをやっているあいだは、次にやることを考えない
集中するとは、いまここで、全身で現在を生きること
と示しています

あ・・・
確かに、人の話を聞きつつ、
「次にこれ話しよう」
と考えている時が、よくあるかも。。。

うん、うん
あるよねー
そのような時は、話を聞くことに集中していないってことですねー

そうかー
人の話を、何も考えずに、集中して聞くって
結構、難しいかも

そうですねー
だから、Frommは
「自分に対して敏感にならなければ、集中力は身につかない」
としています
そして
「あらゆる場面で客観的であるよう心がけなければならない」
「どういう時に自分が客観的でないかについて敏感でなければならない」
としています
つまり、
集中するということは、
自分の心が客観的(理性的)であるかどうかに敏感であり、
客観的(理性的)に保つためには
忍耐、つまり我慢することが必要
ということなのだと考えます
(3)何かを達成するためには忍耐が必要である
Frommは
「忍耐」を「時間をかけて取り組むこと」と考えているようです
Frommは「忍耐力」の例えとして、懸命に歩く幼児を例にあげています
転んでも、転んでも、転んでも、決してやめようとせず、だんだん上手になって、ついに転ばずに歩けるようになる
おとなが自分にとって大事なことを追求するのに、(上記のような)子供の忍耐力と集中力を持ってすれば、どんなことでもなしうるのでは
とも、Frommは示します
先ほど示したように、「精神を集中する」こととして「相手の話を聞くこと」で、忍耐について考えてみます
ここでの「聞く」は「聴く」「傾聴する」ことと考えられますが、このことは簡単にできそうなことでしょうか
「聴く」「傾聴する」というのは、相手の話を聞いているときに、
「えー、それは違うんじゃないかなぁ」
「早く終わらないかなぁ」
「次にこれを伝えよう」
などと考えるのではなく、
「相手の話を、その時の状況を思い浮かべながら、相手に寄り添って話を受け止め、共感すること」と考えます
つまり、ロジャースが示す「相談を受ける心構え」の
1 一致性、純粋性
2 受容、無条件の肯定的配慮
3 共感的理解
と同じようなことを示していると考えます
※「相談を受ける心構え」に関しての詳細は以下を参考に
この傾聴をしていると、相手の話に、気持ちが落ち着かなくなったり、相手の話から別のことを連想してしまうなど、様々なことが頭をよぎっていきます
そのため、集中して聴くためには、自分の頭に浮かんでくる考えを消し去り、目の前の人の話に集中する忍耐力が求められます
(4)技術の習得に最高の関心を抱くことも、技術を身につけるための必要条件の1つである
Frommは
もしその技術がいちばん重要なものでないとしたら、その技術を身につけようとしても、絶対に身につかず、達人にはなれない
としています

そうですねー
規律・集中力・忍耐の修練を積むことは、簡単にできることではないと感じますので、とこの「愛する」という技術を磨くことを、「重要なもの」と思わないとできないと考えます

難しいですね〜
人を愛すること
って、とても大切なことだと思います
しかし、このようなきつそうな修練をしないとできないのであれば、
自分に人を愛することってできるのかなぁ

そうよねー
「あの人のこと好き」
というのは「感情」だと思う
だから、「愛する」ということと「好き」は全く異なっているんですよねぇ
「愛したい」と思う人が現れたら、「愛する」技術を磨こうと思うのかなぁ

Frommは、愛の技術の修練にとって欠かすことのできない条件として
思考においても感情においても能動的になり、一日じゅう目と耳を駆使すること
をあげています
さらに
赤の他人を愛することができなければ、身内を愛することはできない
ともしています
このことから考えますと、「愛する」とは対象の問題ではなく、自分自身が、いつでも誰に対しても行う能動的な行動です
これって、とっても難しいことかもしれませんねぇ
今まで、こんなことを考えたこともないかもしれないですからねぇ
なので、「愛する」ことができるようになる修練をしていくことで、「愛する」ことが少しずつできるようになってくるよ、ということをFrommは伝えたいのかなぁ、と思っています
いちばん重要なものと判断するには、信念と勇気が必要となります
(5)愛の技術の修練には、「信じる」ことの修練が必要である
Frommは
・自分自身を「信じる」とは、自分のなかに、一つの自己、いわば芯のようなものがあることを確信する
・自分自身を「信じている」者だけが、他人に対して誠実になれる
としています

これは、アドラー心理学の「自己受容」と同じようなことを示していると思います
「自己受容」については、以下を参考に

そういえば、アドラー心理学にも
「勇気」
という言葉がありましたねー

うん、うん
「嫌われる勇気」

お、よく覚えてますねー
「勇気」に関してFrommは
「信念をもつには勇気がいる」
とし、
「勇気」とは、あえて危険をおかす能力であり、苦痛や失望をも受け入れる覚悟
としています
そして
ある価値を、これがいちばん大事なものだと判断し、思い切ってジャンプし、その価値に全てを賭ける勇気
としています
Frommは
愛するということは、なんの保証もないのに行動することであり、こちらが愛せばきっと相手の心にも愛が生まれるだろうという希望に、全面的に自分をゆだねること
としています

つまり、「信じる」と「勇気」の修練は
人を愛することで相手にも愛が生まれるということを信じ、勇気を持って愛する
という修練を行っていくということと考えます
まとめ
今回は、Erich Frommの「愛するということ」を題材に、「愛する」とはどんなことか考えてみました
人を「愛する」ようになるための3つの方法として
1 「愛する」とは技術である、ということを知る
2 愛の理論(愛は何よりも与えることであり、もらうことではない)を知る
3 愛の修練を行う
がありました
最後に、
Frommは、
「心理学の究極の帰結は愛である」
としています
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
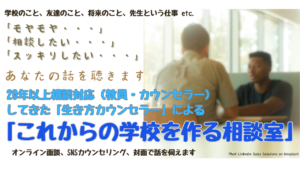
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照:
紀伊国屋書店「新訳版 愛するということ」Erich Fromm(2019年)
集英社「推しの子」赤坂アカ✖️横槍メンゴ(2020年〜)
ダイヤモンド社「嫌われる勇気」岸見 一郎 , 古賀 史健(2013)
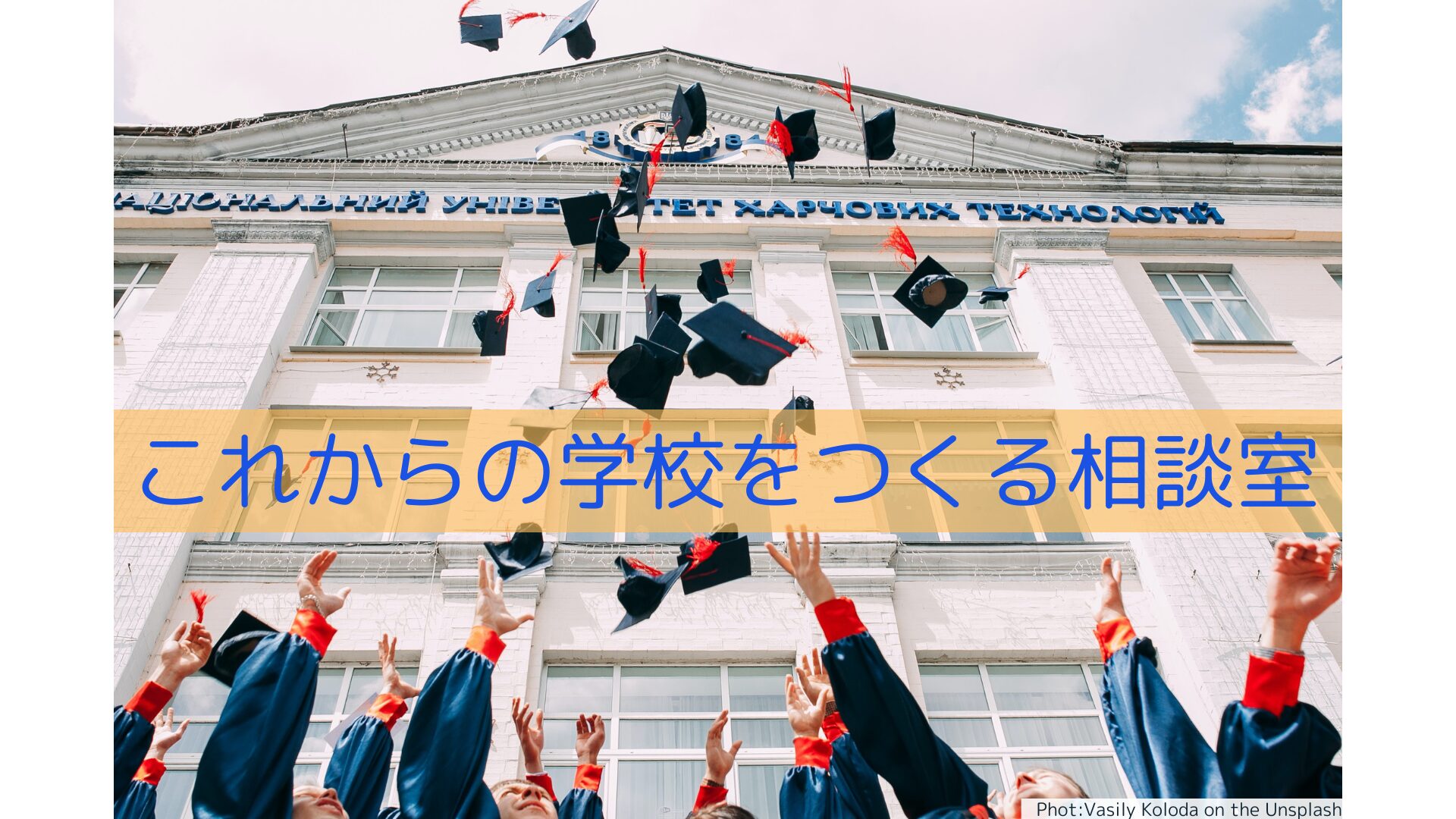








コメント