こんにちは
とも@生き方カウンセラーです
春休みや夏休み、ゴールデンウィークなどの長い休み明けには

学校に行きたくなーい

仕事に行きたくなーい
と感じる人は多いかと思います
もちろん、それ以外でも、「しなければいけないとは、わかっているけど、したくない・できない」という時もありますよねー
そのような場合に、次の3つはいかがでしょうか
1 話をする
2 SNSカウンセリングなどで、かき込みをする
3 何もしない
0 「しなければいけないのに、したくない・できない」という状況について
これまでの教員生活の中で、このような子供たちをたくさん見てきました
このような子供たちの話を聞くと、多くが「理由はわからない」と語っていました
社会人になった彼らと話をしても、「あの時学校に行きたくないと思った理由はわからない」と語る場合もありました
また、SNSカウンセリングをしていると、「会社に行きたくない」と語る方にも出会います
このような方々からは、「人付き合いが難しい」「何のためにこの仕事をしているのかわからなくなった」など、コミュニケーションのことや、将来のことへの不安が出てきます
漠然とした不安や、人付き合いや仕事などへの不安が高くなると、学校に行かなかったり、仕事に行かずに家にずっといるという状況になることもあります
※不安が高くなった方への対応の方法としては、次のものを参考にしてみてください
このような状態が「不登校」や「引きこもり」になると思います
「不登校」や「引きこもり」について、統計的に見てみます
文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると
小中学校の「不登校(統計上は、病気と経済的理由を除いて30日以上の欠席した児童生徒を示しています)」の理由として
令和4年度(2022年度)の不登校の小中学生 およそ29万9千人のうち、その要因は
無気力・不安 51.8 %
生活リズムの乱れ・あそび・非行 11.4 %
いじめを除く友人関係をめぐる問題 9.2 %
となっていました
「引きこもり(就学や就労、交遊などの社会的参加を避けて、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態)」については、厚生労働省(2016)と(2019)より
15歳から39歳 推計数54万1千人
・引きこもりになったきっかけ「不登校」、「職場になじめなかった」「就職活動がうまく行かなかった」等
40歳から69歳 推計数61万3千人
・引きこもりになったきっかけ「退職」、「人間関係がうまくいかなかった」「病気」等

「不登校」や「引きこもり」の要因やきっかけは様々ですが、他の人との良好な関係を続けていくことが難しくなっていきそうですねー
Alfred Adlerは、「すべての悩みは対人関係の悩み」としました
そして、「孤独」つまり「他の人に相談できない」という状況において、人は悩み、不安になっていきやすいと思います
そこで、「他の人に相談できる」方法として、3つの方法をみてみましょう
1 話をする
「相談する」、つまり「話をする」ことです

えっ?
それができないから悩んでいるのに?

確かに
そうですよねー
話ができないから悩んでいるのですよねー
「話をする」ことができるのであれば、「孤独」ではないですよねー
では、「話ができない」という状況になったのは、どんなことがあったからなのでしょうか
「友人を作るのが苦手」
「友達と思っていた人から裏切られた」
「一人暮らしをしている」
「親や兄弟から、絶縁状態になっている」
などなど、様々な原因が挙げられると思います

できないことの理由は、たくさん挙げられるんですよねー
なので、「話をする」方法を考え、実際にやってみることをお勧めします
その結果、うまくいけば、「孤独」にならないことにつながっていきます
しかし、うまく行かない場合、結果的には、現状維持という状況となると考えます

現状維持?
違うよ
話しかけても、話を聞いてもらえないと、「やっぱり、自分の話は聞いてもらえない」って、さらに悲しくなり、余計に、誰とも話をしたくなくなるんだよ〜

そうかもしれないですね
なので、児童生徒であればスクールカウンセラーや地域の教育委員会のカウンセラーを利用したり、会社員であれば、産業医やキャリアコンサルタント、カウンセラーを利用すると、話をしっかりと聞いてもらえます
他にも、厚生労働省が紹介しているところとして、電話相談窓口があり、そのようなものを利用するのも「話をする」方法と思います
ー話をすることのメリットー
心理学的に、話をすることで、どんなメリットがあるのでしょうか
自分のことを話すこと、語ることを、「ナラティブ」と言います
「ナラティブ」は、様々なカウンセリングの中で使われている方法の1つです
過去に起こった様々なことを、現在の自分が語ることで、いくつかの過去の出来事を結びます
その結果、今の自分から考える過去のことを整理し、未来に向けてどうしていきたいかを考えることにつながってきます
自分の生き方は自分で考える、つまり「答えは、自分の中にある」ので、それを見つけていく方法として、大切なのが「話すこと」と考えます
「話をする」ことができない場合、「かく」によっても、自分のことを考えることにもつながってきます
2 SNSカウンセリングなどで、かき込みをする
どうしても、「話をする」ことが難しい方は、「SNSカウンセリング」などでかき込みするのはいかがでしょうか

うん?
「SNSカウンセリング」って、何のこと?
「SNSカウンセリング」とは、LINEなどのSNSやインターネットのメッセージ機能を用いて、文字でやり取りをしながら行なっていくカウンセリングや相談のことです
厚生労働省は、このようなところを紹介しています
SNSカウンセリングのメリットとして次のようなことが挙げられます
・自分の好きな時間にできる
・文字にすることで、自分の発言やカウンセラーの言葉を可視化し、繰り返し見ることができる
・文字にすることで、自分の考えを整理することができる
・本名や自分の姿を表さずに、カウンセリングを受けられる
・カウンセリングを途中で辞めたい時は、すぐに辞めることができる
「話をする」「SNSカウンセリングにかき込む」という2つの方法を紹介してきました
しかし、これら2つができそうもない場合、「何もしない」という方法もあります
3 何もしない

え?
何もしないって、どういうこと?
「何もしない」ということは、「ボーッとする」ということ
・人と話をしない
・ゲームやスマホなどを触ることをしない
・本を読まない
・音楽を聞かない
ということです

こうすることで、「行きたくない」という思いへの対応策になるの?
何かすることはないの?

確かに
「〜しない」だけでは、「っで、どうしたらいいの?」ってなりますよね
スマホを置いて、
海にいく→そこでボーッとする
山の頂上にいく→そこでボーッとする
森の中で寝転ぶ→そこでボーッとする
河岸に腰掛ける→そこでボーッとする
公園に行く→そこでボーッとする
など、正確にいうと、この「何もしない」というのは「自然の中で、心と身体をリラックスさせる」ことです

自然の中に行くことで元気になることから、「ヒーリング」、「パワースポット」や「マイナスイオン」などという言葉が、自然とも結び付けられてきました
この辺のことは、私は詳しくありません
しかし、自然の中にいると、心が落ち着いたり、何かをしてみようという気持ちになることがよくあります
もしかしたら、このような前向きになれるのは、自然という大きな力が何かを持っているからかもしれないと思います

このようなことを「自然セラピー」としている方がいらっしゃいました
また、「スマホを置く」というところも、キーワードと思っています
一時期話題になった「スマホ脳」という本などでも、「スマホ」と「脳」の関係について、示されておりました
現代人の脳は、様々な刺激にさらされています
スマホを置くことで、情報を取り入れることを遮断し、
脳を休めることで、心も休められるようになってきます

心は、脳が作り出してますからねー
まとめ
今回のまとめです
「学校に行きたくない」「仕事に行きたくない」など、「しなければならないけど、したくない・できない」場合の対策としては、
1 話をする
2 SNSカウンセリングなどで、かき込みをする
3 何もしない
があると考えます
いずれにしても、
自分の心・脳を整理して
自分の生き方について考えること
で、自分がした方がいいことがみえてくると思います
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
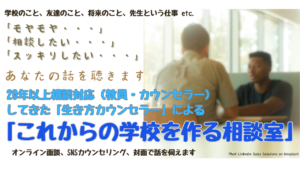
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照:新潮新書「スマホ脳」アンデシュ・ハンセン(2020年)
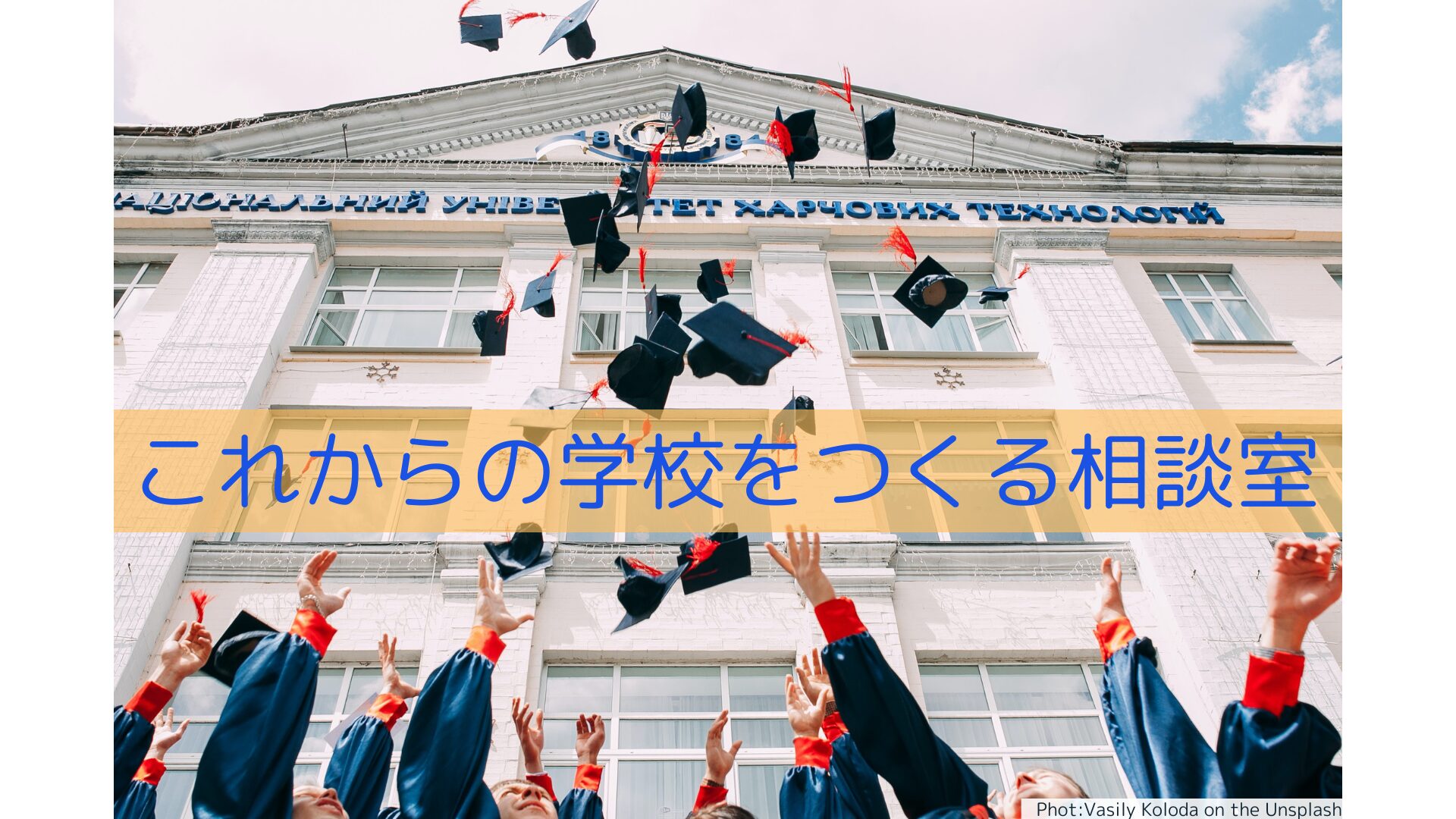







コメント