こんにちは
管理者 とも@生き方カウンセラーです
さて、学校や企業などの管理職や、キャリアカウンセラーの中には、「仕事にやる気を出させるにはどうしたらいいんだろう?」「やりがいを感じるって、どうしたらやる気のない社員にやる気をもたすことができるんだろう?」「そもそもどんな動機があれば成功するんだろう?」など、に悩まれている方はいらっしゃると思います
欲求理論のDavid C. McClelland(以下、「McClelland」とします」より「三つの鍵となる動機が仕事へと駆り立てる」としております
McClellandは、「人びとの動機こそが仕事場で成功するかどうかの最良の預言者」とし、仕事の達成度を左右する「力への欲求」「達成への欲求」「帰属への欲求」の三つの欲求を示しました
「これらのうちのひとつが主導的なものとなり、仕事場での当人の作業効率をかたちづくる」としました
「力への欲求」とは「他者を支配したいという欲求」であり、これこそが、良いマネージャーないしリーダーにとって最重要な動機づけと考えました
しかし、これが正しいのは、あくまでこの欲求が会社あるいは組織のために発揮されるかぎりのことです
個人的に強い権力を持つ人間は、チームプレイヤーとしては使えないこともあります
「達成への欲求」とは、「人びとが新たな目標へと手を伸ばし、向上してゆく助けをすることで、人々の競争心を駆り立てる欲求」としました
これにより、質の高い仕事が生まれます
そのため、この欲求は、知能よりもずっと正確な仕事の成功・不成功の預言者となります
「帰属への欲求」とは、「他者との良好な関係を保ちたいという欲求」で、これによって人びとはチームを組んできちんと仕事ができるようになります
そして、帰属への顕著な欲求をもつ人びとが有能なマネージャーになることはまずないとも言われています
McClellandが指摘するのは、動機づけは無意識のうちに深く埋め込まれた人格的特性に由来するという点でした
そのため、McClellandは、主題統覚検査(TAT)を活用し、その答えを分析し、検査を受けた人びとの適合性を比較できるようにしました
私自身としては、動機づけが下がっていたり、何をしたいかわからなくなったときには、自分の気持ちを整理するために、旅行などに行って行う気分転換やマインドマップの作成などをしたり、やりたくなるまでやらない、などの方法をとっております
そうすることで、自然と自分が向いて行きたい方向が定まり、「達成の欲求」が強くなってきます
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
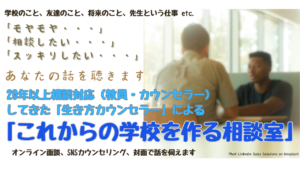
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照 三省堂「心理学大図鑑」(2013年)
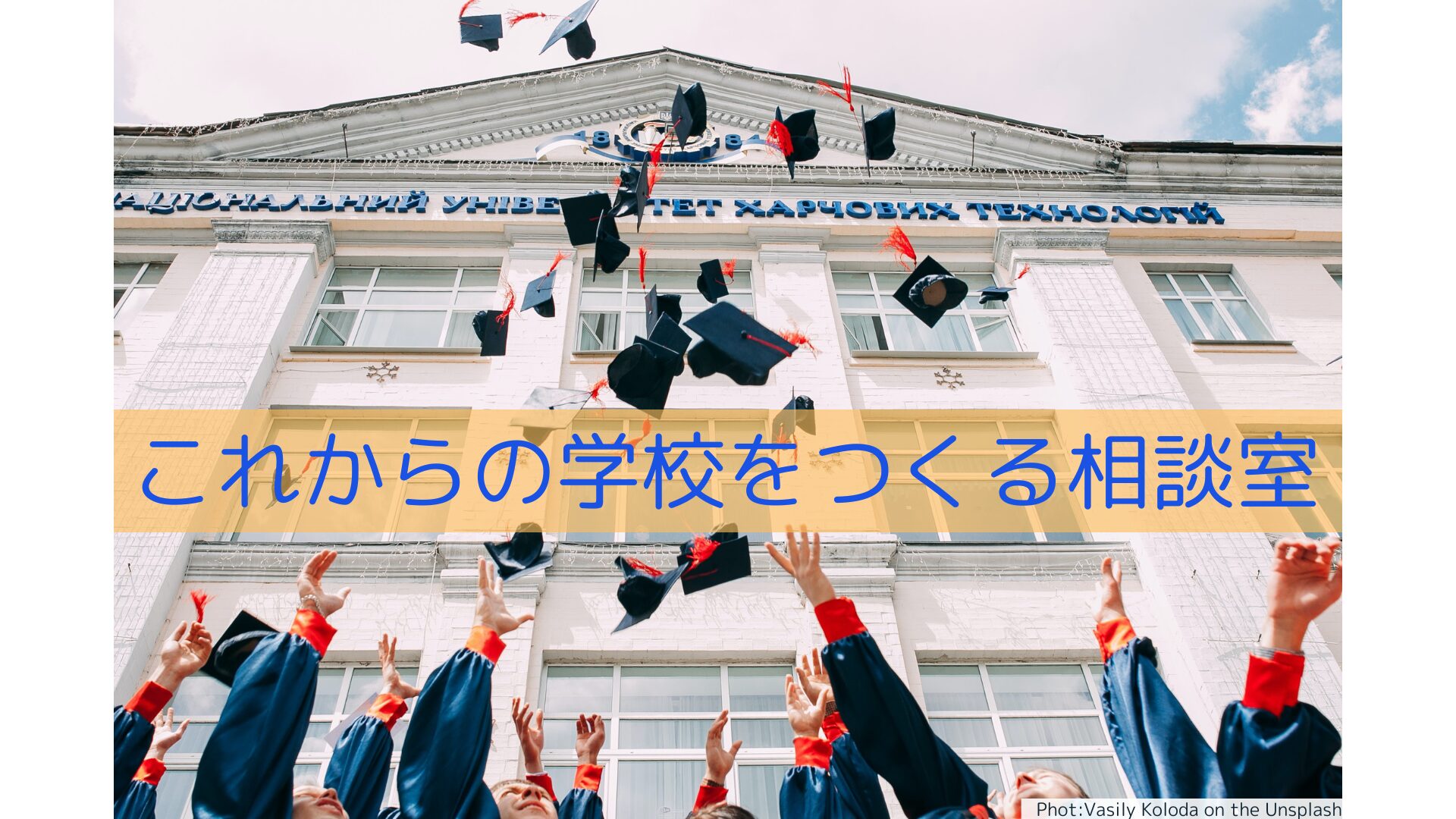




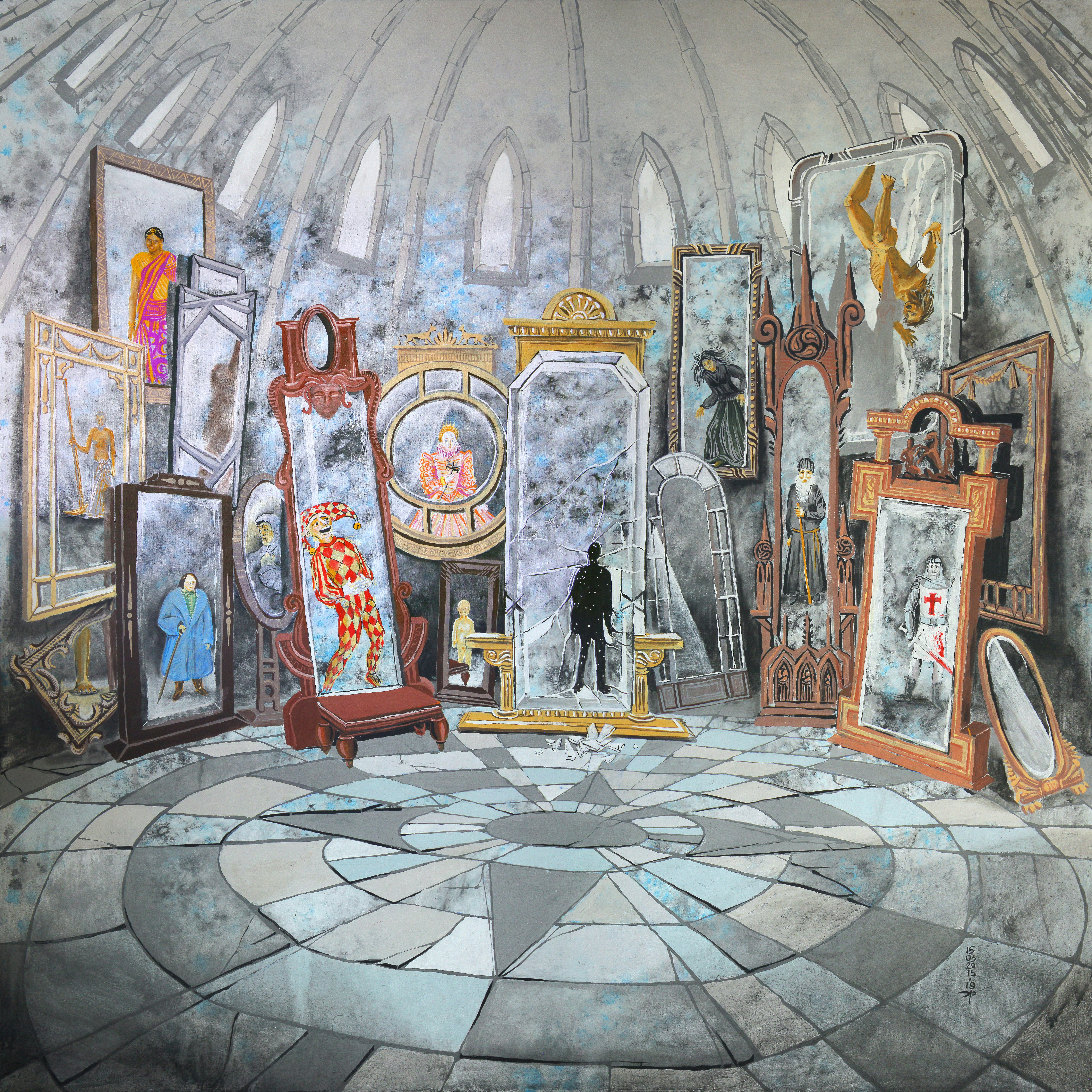

コメント