こんにちは
管理者 とも@生き方カウンセラーです
接客の仕事や学校の子供対応などしているときに、怒られたり、泣かれたりなど、「感情が不安定」な相手に遭遇し、「モヤッ」と思う場面があると思います
このような人と、今後も関わらないといけない場合の方法として、次の3つが大切と考えます
(1)謝らずに、相手がその事実から考えたことを聞く
(2)自分が感じていることを伝える
(3)距離をとる
※まずは、「感情が不安定の極端な場合」についてお伝えします
感情が不安定な方が「今後も付き合っていきたい人」や、「付き合わなければいけない人」の場合の対応は、こちらをクリックしてください
1 感情が不安定の極端な場合として考えられること
まずは、感情が不安定の極端な場合として、
「人が変わる」ように感じる「多重人格」
があると考えます
私は、幼い頃から「人が変わる」ということに興味がありました
それは、「ルパン三世」「少年探偵団」や赤川次郎さんの作品などの漫画や小説などのように、犯人が変装などをして、正に「いろんな人に変わる」不思議さが、最初だったと思います
私が成長していく中で、あのようにうまく変装して、変わることができないことを知っていきました
その後、「多重人格」という言葉に出会いました
特に、このことを詳細に書いた本で、私が初めて出会ったのが、「24人のビリー・ミリガン」でした
この本は、とても衝撃的でした
「こんなことがありえるんだ
子供の時に、恐怖から逃げるためにどうしたらいいのか、ということをきっかけに」ということを思ったことを今でも覚えています
特に、こども園の保育士や学校の先生など、子供と接する仕事をされている方々や、児童福祉司や刑務官の方々には、「突然、豹変した子がいた」「今まで仲良くしてたのに、何で怒っていたんだろう」「多重人格なのかなぁ」など、ふと思った方もいらっしゃるかと思います
精神障害が専門のCorbett H. ThigpenとHervey M. Cleckley(以下、「ThigpenとCleckley」とします)より「イヴには3つの顔がある」としてます
多重人格障害(MPD、のちに解離性同一性症)は、1791年初めて報告されて以来、150年の間に100以上の臨床例が報告されています。原因は幼児期の虐待にあります
MPDの最も知られた症例の1つが、イヴ・ホワイトでした
最初の報告は、1952年にThigpenとCleckleyによってされました
イヴは、医師に次のような病気のエピソードを語りました
着るはずもない飛びっきり高価な服を何着も、そもそも払うお金すらないのに購入したと
この話を物語っている途中で、彼女の態度が急変しました
一瞬混乱したように見えたが、その後では顔の輪郭線まで一変しました
眼は見開かれ、挑発的な笑みが浮かんでいました
急に歯切れのよい、くだけた口調で話だし、イヴはそれまで喫煙したことなどなかったのにタバコを要求しました
これが「イヴ・ブラック」です
その後、治療をしていく中で、イヴが失神をしました
起きた時には第三の人格「イヴ・ジェーン」になっていました
彼女は、イヴ・ホワイトより受容能力があり興味深い性格をしていました


「目の前の相手は、どんなことを考えているんだろう?」
MPDは稀です
しかし、私たちの身の回りにも、突然怒りだしたり、泣き出したりするような感情の起伏の激しい子供や大人もいると思います
彼らは、彼らの過去の経験から何かを感じ、そのような感情的な行動になっていると思われます
MPDの主な原因としては虐待などで、
そのままその行為に直面していると「このままでは自分自身の精神を壊してしまいそう」と感じ、そうならないために、「別の人格になる」
と考えられております
このことから考えると、突然に怒り出すというのは、「そうしないと、自分自身の何かが傷つけられてしまう」と感じて、自分を守るとために、「突然怒る」という態度になっていると考えられます
このように書くと、「そんないろいろなことを考えていないよ。だって、突然怒るんだから」というご意見もあるかもしれません
アドラー心理学で有名なAlfred Adlerは、

「大声を出すために、怒る」
「怒りという感情を捏造する」
ということを示しております。
つまり、

「人が感情的な行動をするのは、そうすることで、感情的な行動をとった人にとって利益がある。だから、感情的な行動をする」
そうです
「感情的な行動をとった人にとっての利益」の例としては、
①相手が自分の気にしていることを言った
②相手を罵倒した
③相手は謝り、自分に屈服し、従う
といったことです
この過程によって、怒った人の気持ちは、
相手が自分に屈服する・従う→自分が立場的に上になる→自分は傷つかずに守られる
というような変化が起こってくると考えます
あなたにとって、このような感情の起伏が激しい人が、どのような人なのかによって対応の仕方は変わってくると考えます
次の2通りの場合を考えます
①今後も付き合っていきたい人、付き合わなければいけない人
②短い付き合いでいい人
2 今後も付き合っていきたい人、付き合わなければいけない人
この場合、相手の感情の起伏を気にされない方もいらっしゃると思います
その方は、今のままで良いのかもしれません
相手の感情の起伏を気にされる場合、今後も長い間付き合っていくために、相手に振り回されていると感じ、ご自身も疲れてしまうと思います
しかし、「相手とは、今後も付き合っていく必要がある
でも、自分の疲弊感もしんどい
だから、「相手の感情の起伏が少し落ち着いてくれたらいい」を望むと思います
その場合、
(1)相手が望んでいる(「謝る」など)ことをせずに、相手の感情が変化した原因となった事実からどんなことを考えたのかを聞く
(2)自分が感じていることを伝える
の2つの行動をする方がいいと思っています
(1)謝らずに、相手がその事実から考えたことを聞く
「怒らないで」と相手に行動を変えるように言っても、多くの場合は変わらないと思います
「人の行動を変えるのは困難」だからです
人が行動を変えるかどうかは、その人次第であり、他の人が変えることはできません
なので、相手に変わってもらうことを期待するよりも、自分ができる行動を変えていった方がうまくいく場合が多いと考えます
そこで、自分ができることとして、「相手が望んでいることをしない」があります
これは、相手が意識的にしろ、無意識的にしろ、望んでいることは、立場的にあなたよりも上にいることです
先ほどの通り、怒った人の気持ちは、
相手が自分に屈服する・従う→自分が立場的に上になる→自分は傷つかずに守られる
となっていくと考えます
そこで、この「謝られる」という行為がないと、「相手が従う」という目的に辿り着かないのです
そのため、いずれ、あなたに対して「怒る」ということはしなくなる場合が多いです
しかし、「目の前で、相手が怒っているから、少し気分を落ち着かせたいから、謝るんだよ」という方もいらっしゃると思います
気分を落ち着かせるのであれば、「どんな事実に対して、どのように考えたから怒っているのか」を聞いていく方が、いいかもしれません
この際には、「なぜ?」は使わずに、
「どんなことを考えたの?」「どんなところから?」
と「なぜ?」を使わない方が得策です
「なせ?」を連発すると、詰問されているように感じ、相手を余計に苦しめてしまうことも多々あるからです
また、場合によっては、このように相手の考えを聞いていく対応をしていくことで、同じ話が繰り返しする「無限ループ」になることもあります
このようにずっと、同じ話の繰り返しなのは、「自分の話が伝わっているのかどうかわからない」と言ったことがあります
そこで、相手の話を要約し、「このように、自分は認識しているけど、そう?」などと、相手の話が伝わっていることを示していくことで、いつまで続くかわからない繰り返しを防げることもあります
(2)自分が感じていることを伝える
相手の話を聞いて、自分自身が感じていることや、感じたことを伝えるのも大切です
例えば、怒られてびっくりしたこと、相手から怒った理由とその時の想いを聞いてくこと感じたことなどを伝えていきます
そうすることで、自分自身の気持ちに正直になれ、あとで、自分の気持ちの中にしこりができるのを防ぐことにつながってくると思います
「自分が我慢すればいいんだ」という考えになる方もいらっしゃると思います
これは、短い付き合いの相手であれば、いいかもしれません
しかし、長期に渡って付き合うのであれば、この我慢の積み重ねにいずれ耐えきれなくなる日が来ると思います
なので、少しずつ溜め込むのではなく、小さいうちに外に出すことをお勧めします
また、自分の気持ちを伝えていくことで、それを聞いた相手にも、様々な考えや想いが浮かんできます
もし、あなたと関係を継続していきたいと考える相手であれば、そうなる方法について考えてくれると思います
3 短い付き合いでいい人
感情の起伏が激しい人が、あなたにとって、短い付き合いでいい人の場合は、その相手と距離をとることをお勧めします
(3)距離をとる
「短い付き合いでいい人」の場合、距離をとりましょう
(1)や(2)の対応は、どうしてもあなた自身のパワーを使い、疲れることもあります
でも、そのように疲れても、長く付き合っていく相手になら、力を使うことはできると思います
しかし、長く付き合う必要がなく、短期的な付き合いしかしないのであれば、できるだけ、そのような人とは距離を置く方が、あなたの気持ちも安らぐと思います
世の中には様々な人がいます
付き合う必要がない人や、あなたに合わない人もいます
あなたの気持ちを見出す方は、「付き合う必要がない人」なのかもしれないです
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
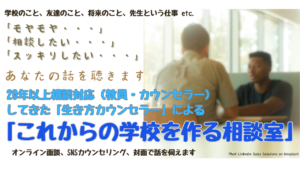
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照 三省堂「心理学大図鑑」(2013年)
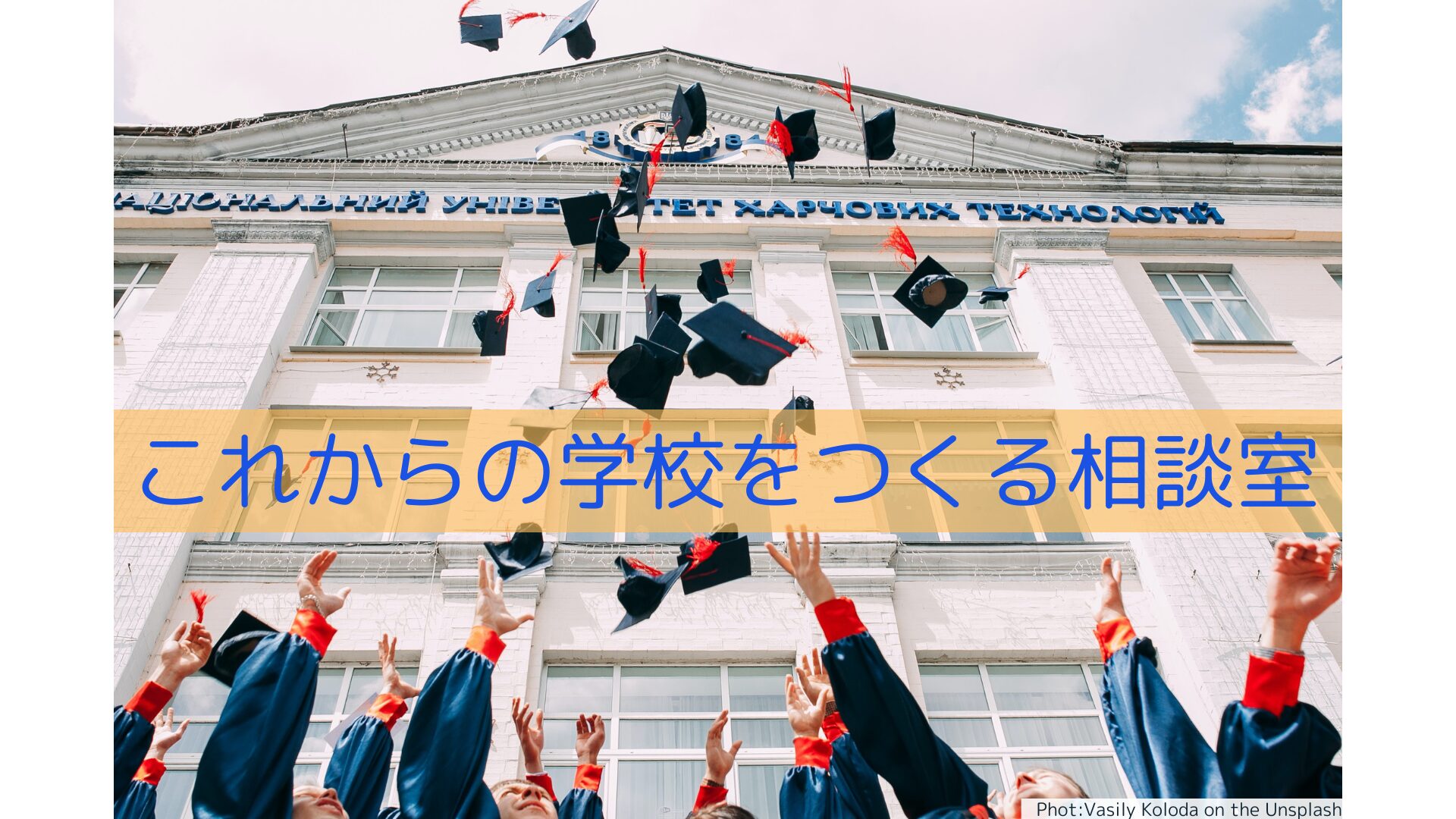






コメント