こんにちは
管理者 とも@生き方カウンセラーです
子育てや子供たちの対応をする仕事をしていて、「我慢してー」と思う場面って、たくさんあると思います
では、「我慢する」ことが苦手な子供に、「我慢できる」ようにするためにはどうしたらいいのでしょうか。次の3つが大切と考えます。
1 ちょっと後のことを考える習慣をつける
2 我慢を望む大人自信の気持ちをリフレッシュする
3 1と2を、子供やパートナー等と一緒に楽しみながら考える
Walter Mischelのパーソナリティ理論
気になったニュースの1つに、10代の4名による「銀座の強盗事件」があります
これが気になったのは、色々あるのですが、「一番は10代の若さで、こんなことをやってしまい、今後どうしていくのだろう」と思ったところです
「何が良くて、何が悪いのかは個人の判断」の時もありますが・・・
どんなことを考え、どんな判断からこのような事件になっていったのか、見守ってみたいと思いました
こども園の保育士や学校の先生など、幼い子供と接する仕事をされている方々には、子供たちが遊んだり、学んだりしている中で、「この子、お菓子に釣られないんだぁ」「小さくても、誘惑にのらないなんて」「こんな我慢ができる子って、もしかしたら、将来すごい人になるのなぁ」などと考えられたこともあるのではないでしょうか
パーソナリティ理論のWalter Mischel(以下、「Mischel」とします)より「誘惑に耐えられた子どもの方が心理学的により良い順応を示し、より信頼の置ける人間になった」
Mischelが、「パーソナリティ理論」の中で、古典的な人格検査法はほとんど無価値だと言い切ることでパーソナリティ理論の世界に大きな波紋を投げかけました
Mischelは、人格検査法尺度から行動を予測しようと試みた数多くの研究を再調査し、その時代においてそれらの精度が9 %にすぎなかったことを明らかにしました
Mischelは「環境からのきっかけを欠いた行動は、不条理なまでに混沌としている」「人格検査はじつのところ個人について何を私たちに語っているのだろうか」としております
Mischelの注意を惹いたのは、行動決定に際して、状況のような外的要因が果たす役割でした
いろいろな状況でくりかえし観察される人間の行動を分析すれば、人格特性のリストとは矛盾するかもしれないが、行動パターンを読み解く鍵が与えられ、人格の行動分析が明らかになる可能性でした
そのためには個人の状況解釈も考慮に入れられると、Mischelは提起しました
そして4歳の子どもたちの前にマシュマロを1つ置き、「すぐに食べる」か、「20分待ったら、2個食べられる」の選択をさせたそして、それぞれの子どもが思春期になるまでの追跡調査をするといった「マシュマロ実験」を行いました。
この結果、我慢することができた子どもたちの方が、学校でのおこないも良く、社会的にも能力を発揮し、自己評価もできていました。
満足を遅らせられるということが、これまでに計測されたいかなる特性よりも、将来の成功の預言者となったようです。

1 ちょっと後のことを考える習慣をつける
4歳ぐらいの子供が「我慢できる」ようになるには、どうしたらいいのでしょうか
このように考えた時には、まずは、「我慢ができる」ということを考えた自分自身の気持ちを感じていただきたいです
「この目の前にいる(我が)子に、我慢してほしいと考えているのは、どんなことを考えてかなぁ」と
例えば、
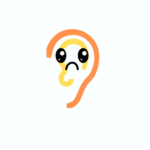
「すぐに出かけたいのに、テレビを見て動かない」
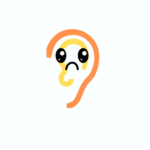
「野菜を食べてほしいのに、食べてくれない」
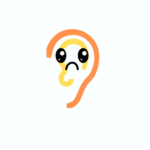
「もう寝る時間なのに、遊びが終わらない」
などのようなこともあるでしょう
このような場合、実は、困っているのは、子供ではなく、大人(主に保護者)になると思います
大人は、「先を見て考える」から、このように困ってしまうのでしょう
ということは、子供にも、「先を見る」習慣を身につけさせていくことが、「我慢できる」子供に育てる方法の1つと考えます
2 我慢を望む大人自信の気持ちをリフレッシュする
親が困るのは、親自身の気持ちや時間に余裕がない時に、困っていることも考えられます
例えば
「もう、次のことをしないといけないのに」

「仕事でうまく行っていない・・・」
「子供が寝てから、やらなきゃいけないことがいっぱいある・・・」

「子供が寝てから、やらなきゃいけないことがいっぱいある・・・」
このような、「焦っている」「困っている」心理状態では、自分とは異なる相手のことを考えることは難しいように感じます
なので、このような気持ちになっている時には、気分転換などのリフレッシュやクールダウンが大切に思います
そのために、周囲の人に、ご自身のことを伝え、協力してもらえるようにしていくことが必要になってくると思います
3 1と2を、子供やパートナー等と一緒に楽しみながら考える
自分の事情を「知らない」「わからない」子供を相手にしている場合に、「焦っている」「困っている」心理状態では、余計にイライラしてしまうこともあるのではないでしょうか
実は「知らない」「わからない」というところが、自分中心的になっている場合があります
本当は、「相手にわかるように伝えていない」だけかもしれません。目の前にいる子供が理解できるような言葉や例えを入れながら、事実と自分の気持ちを伝え、解決方法を一緒に考えてみましょう
子供を相手にしている大人が、ご自身以外のパートナーであったり、職場の同僚の場合には、ぜひ、その方々とも一緒に解決方法を考えてみてください
その方法が、大人と子供にとって、リフレッシュにつながる方法や、楽しんで行える方法であれば、余計にいい方向に進んでいくと思います

この記事を書いていて、4歳の子どもの行動が、思春期の行動を予測できるということに驚かされました
まさに、「三つ子の魂 百まで」といった諺が頭をよぎりました。幼い頃から、その先のことを大切にしながら物事を考えさせていくことが、その子の将来をつくっていくことになりそうな気がします
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
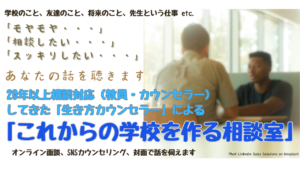
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照 三省堂「心理学大図鑑」(2013年)
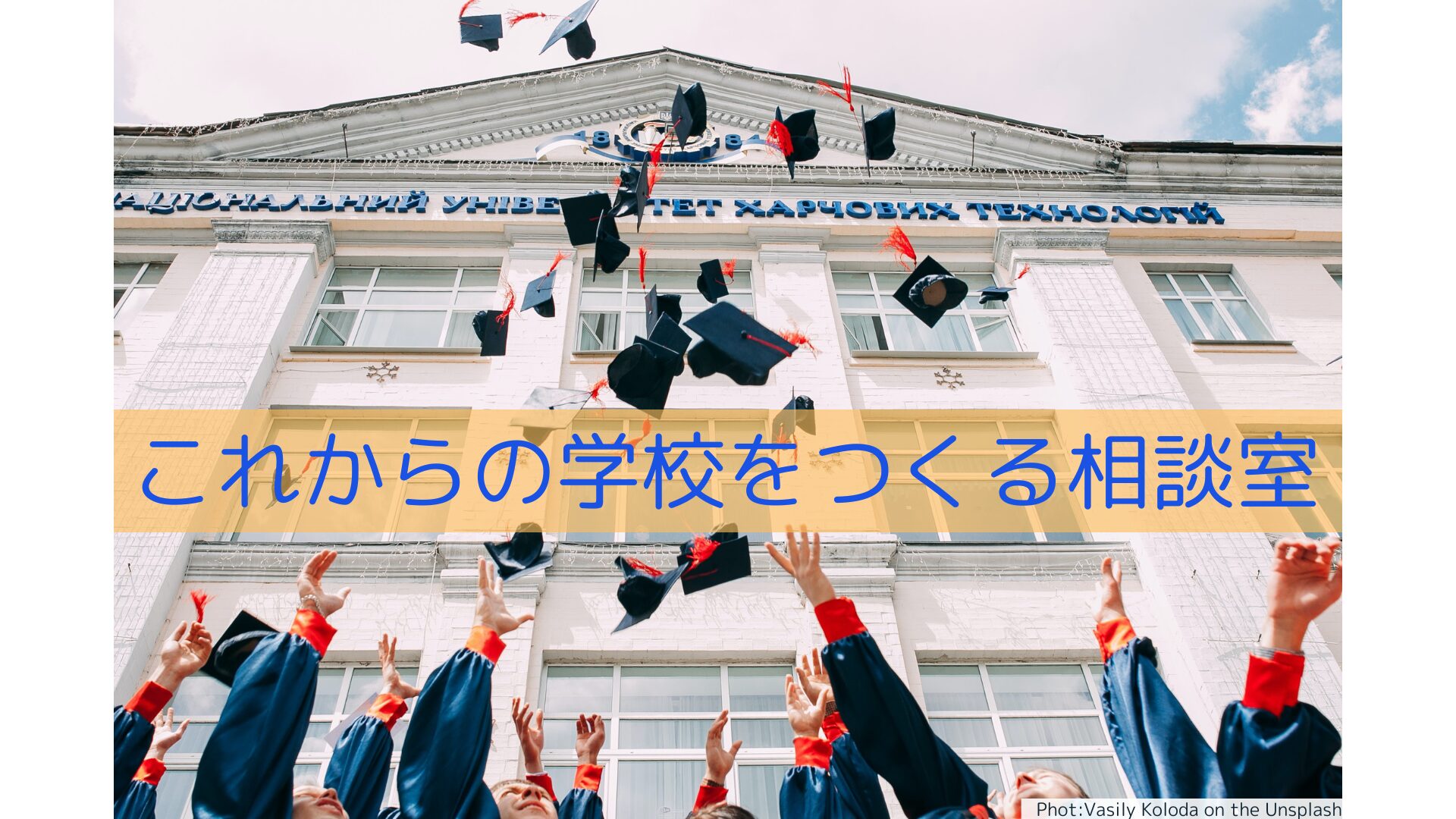






コメント