こんにちは。
管理者 とも@生き方カウンセラーです。
こども園や学校の先生方、お母さん・お父さんたちの中には、子供たちの行動や自分自身の行動、周りの人の行動を見ていて、「どうしてあんなことする(した)んだろう」とか、「男の子(女の子)らしくしなさい、って言われても・・・」など、身につけている行動について、「モヤッ」を感じることもあるのではないでしょうか。
社会的学習理論のAlbert Banduraによると、「人間の行動のほとんどは、モデリングをつうじて学ばれる」としております。
社会的学習理論というのは、Banduraが提唱した考えで、「人びとは、報酬(いいことをしたからご褒美をあげる)と懲罰(悪いことをしたから罰する)といった強化をとおしてではなく、他者の観察をとおして学ぶ」という考えが中核にあります。
そして、他者の行動を守備よく学ぶために必要な4つの条件として
「注意」「記憶の保持」「再生」「動機づけ」
を指摘しています。
学習には、学習者が何よりもまず注意を払い、次に自分が見聞きしたことをちゃんと覚えて、さらにその行動を自分の身体を使って再現します。
そして、このようなことを行いたいと思うしかるべき動機や理由ー例えば、優勝したいや合格したいなどの期待ーが必要ということだそうです。
この社会的学習理論をもとに、「暴力的な映画やテレビ番組が、子どもの暴力傾向を助長するのではないか」と言われることがあります。
確かに、先ほど示した「注意」という点では、目の前の暴力的な情報を取り入れ、「記憶」していくことにつながることにはなりそうです。
しかし、Banduraの考えでは、「子供たちの暴力的行為についての知識が必ずしもみずからそうした行為に加担することを結果するわけではない」としてます。
さらに「子どもが社会の中の攻撃性を学ぶにあたっては、環境的な経験がもう1つの要因になる」としてます。
例えば、戦争など、いつ命がなくなるかわからない危機的な状況下では、そうでない環境に暮らす人々と比べて、暴力行為に加担する可能性ははるかに高くなります。
「男の子・女の子らしい行動」について。
人びとはそれと意識することなく、生まれて以来の子供たちに対する行動を自分自身の性的役割から期待されるものに適合されるようにふるまいます。
その結果、子供たちは性的規範とみなされるものにかなったふるまいをするようしむけられます(例えば、周囲の大人が、おままごとをしている女の子を褒め、同じことをする男の子をさげすむなど)。
もちろん、このような考えへの批判は、いくつもありますが、今でも、Banduraの考えが引用されたり、議論をよんでいるという事実は、彼の影響が大きいことを示していると思います。
最後まで、「これからの学校を作る相談室」をよんでいただき、ありがとうございました
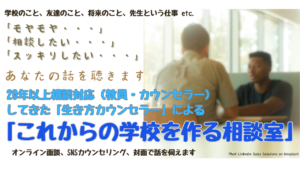
誰かに話をしたり、相談したりすることが、悩みの解決につながります
そのような場合は、「相談の申し込み」をご利用ください。
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照 三省堂「心理学大図鑑」(2013年)
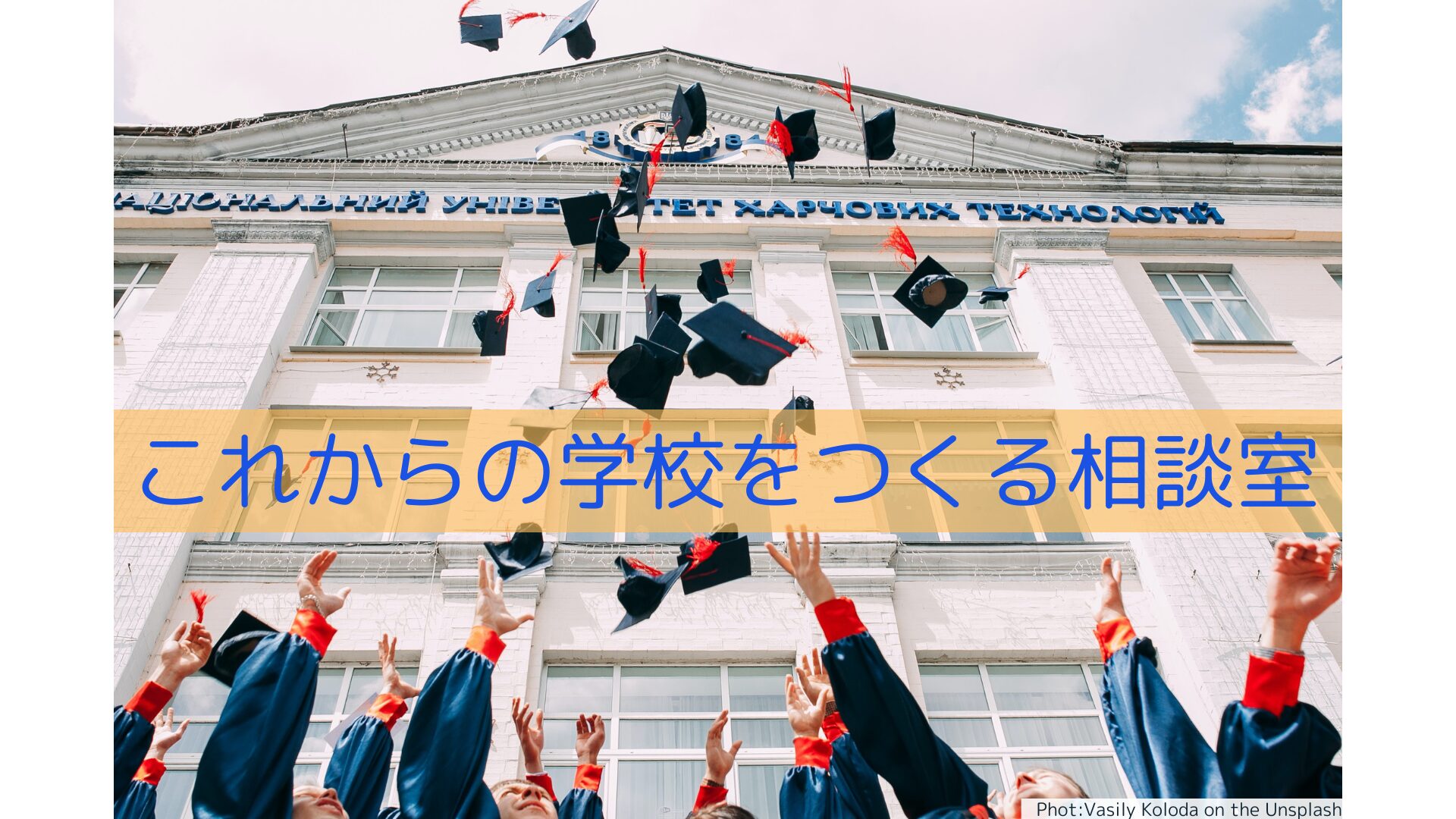





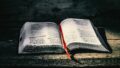
コメント