こんにちは
管理者 とも@生き方カウンセラーです
この言葉は、現在、相談やカウンセリングだけでなく、マネジメントなどに関する本の中でも出てきます
それは、「傾聴」は、相手との信頼関係、つまりラポールをつくりやすくするからです
ラポールが形成されると、相談者は、相談される相手を信頼し、様々なことを話せるようになってきます
その結果、相談者との関係が良くなりやすくなります
また、相談だけでなく、人と話をする際に傾聴をしていくことで、その相手との関係もよくなり、ビジネスなどでうまくいく可能性が上がってきます
そんな魔法のような「傾聴」とはどのように行うのでしょうか。
この方法は、様々な本に記載があります
Weblio国語辞典によると、
とあります
福原眞知子著「マイクロカウンセリング技法ー事例場面から学ぶ」
を参考に、管理者が考える「傾聴」について示していきます
1.基本的傾聴技法ーマイクロカウンセリングよりー
この本の中で、「基本的傾聴技法」として
1)開かれた質問、閉ざされた質問
2)クライアント観察技法
3)はげまし、いいかえ、要約
4)感情の反映
の4つが挙げられ、これらを連続して行っていくことが示されています
1)開かれた質問、閉ざされた質問
⚪︎開かれた質問は、「オープンクエッション」ともいい、「はい」「いいえ」では答えられない質問になります
例えば、「どんな風に?」「何があったの?」などの質問です
⚪︎閉ざされた質問は、「クローズドクエッション」ともいい、「はい」「いいえ」で答えられる質問です

これらの質問技法を習得すると、カウンセラーはクライアントが自分の問題について話すのを促したり、自己探求することを助けることができます。
2)クライアント観察技法
⚪︎クライアントを観察する技法のことです
質問に対するクライアントの応答の言葉と表情・態度との間の矛盾点に気づくなど、カウンセラーとクライアントとのコミュニケーションにおいて”今、ここ”で起きていることへの多くの手がかりを得ることができるようになります
3)はげまし、いいかえ、要約
⚪︎「はげまし」技法は、大きく分けて2つあります
・「言語」によるはげまし:「ええ」「それで?」と言ったものや、クライアントの言葉を短く繰り返すものです
・「非言語」によるはげまし:うなずきのような身体表現で表すものです
⚪︎「いいかえ」技法は、クライアントが語ったことの本質(キーワード)をフィードバックすることです
⚪︎「要約」技法も、「いいかえ」との共通点があります
「要約」の技法は、面接の中ほどや最後に今回語られた内容を対象として用いたり、長期にわたるセッションで語られた内容を対象として面接の最初に用いたりします

これらの3技法を習得することにより、カウンセリングのプロセスを活性化させ、クライアントの状況や気持ち・ものの見方を明確にしながら、面接を効果的に展開して行くことができるようになります。

4)感情の反映
⚪︎「感情の反映」技法では、他の基本的傾聴技法を用いながら、クライアントの言語化されない感情を注意深く観察し、それを手掛かりとしてクライアントの感情に注意を向けてフィードバックしていくことになります
例えば、「クライアント観察技法」によってクライアントが泣き出した様子を捉え、「泣きたくなるほど、大変だったことが推測されます(感情の反映)。どのような感じなのか、もう少し詳しく話していただけませんか(開かれた質問)」
これらを用いて、相談に乗っていくことで、「傾聴」につながりやすくなります
というのも、これはあくまで「技法」です。そのため、「技法」が上手になることで、「傾聴」しやすくなります
2.相談を受ける心構えーロジャース選集よりー
相談を行う際に最も大切なこととして、「相談を受ける側の心構え」と考えます
相談を受ける側が、「相談を受ける心構え」ができていないと、「傾聴」になりにくいと考えます
では、「相談を受ける心構え」とは何でしょうか
それは、
Rogers, Carl. R. (ロジャーズ選集(上):カウンセラーなら一度は読んでおきたい厳選33論文、2001年誠信書房)が示す
1)一致性、純粋性:
相談者との関係の範囲のなかで、一致しており、純粋であり、統合している人間でなければならい
=相談者との関係のなかで、自由に深く自己自身であり、現実に経験していることが、自分自身の気づきとして性格に表現されていなければならない
2)受容、無条件の肯定的配慮:
相談者の経験しているあらゆる局面を、その相談者の一部として温かく受容しているという経験をしているならば、その受容している度合いだけ相談者は、無条件の肯定的配慮を経験している
=(所有的なものでもなく、セラピスト自身の欲求を満足させるものでもなく)相談者を好きである
3)共感的理解:
相談者の怒り、恐れ、あるいは混乱を、あたかも自分自身のものであるかのように感じ、しかもそのなかに自分自身の怒り、恐れ、混乱を捲き込ませていない状態
相談者の世界がこのようにセラピストにはっきりと映り、セラピストが相談者の世界のなかを自由に歩きまわるとき、セラピストは、相談者にはっきりしているものを自分が理解していることを伝えることができるばかりではなく、相談者がほとんど気付いていない自分の経験の意味を言葉にして述べることもできる
のことと考えています
つまり、「相談を受ける心構え」は

「相手の話すことに対して、カウンセラーとしての①自分自身の一致を図りながら、②温かく受容し、③受容したことをあたかも自分のことと理解したことを相談者に伝えようとしている」
と思います

この3つの心構えについて、Rogers, C. Rは、「建設的なパーソナリティ変化※が起こるための諸条件」として、6つの条件を示しており、その中の3つを選んで示しました
詳細は、参考文献をご覧ください
※建設的なパーソナリティ変化:①個人のパーソナリティ構造が、統合性より大きくなり、内面の葛藤が少なくなり、効果的な生き方に用いられるエネルギーが大きくなったと臨床家たちが一致して認めるような方向に変化すること②行動における変化が、一般的に未成熟とみなされる行動から、成熟したとみなされるような行動へと変化すること
友達や仲間との関係、授業や学級づくり、学校づくりを解決すること方法の1つとして、話をすること・相談することがあります
本ブログでは、進路や生き方の悩みに対しての相談を受け付けています

相談をご希望の方は、「相談の申し込み」をご利用ください。
最後まで、よんでいただき、ありがとうございました
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
参照:
福原眞知子「マイクロカウンセリング技法ー事例場面から学ぶ」(風間書房、2007年)
Carl. R. ロジャース「ロジャーズ選集(上):カウンセラーなら一度は読んでおきたい厳選33論文」(誠信書房、2001年)
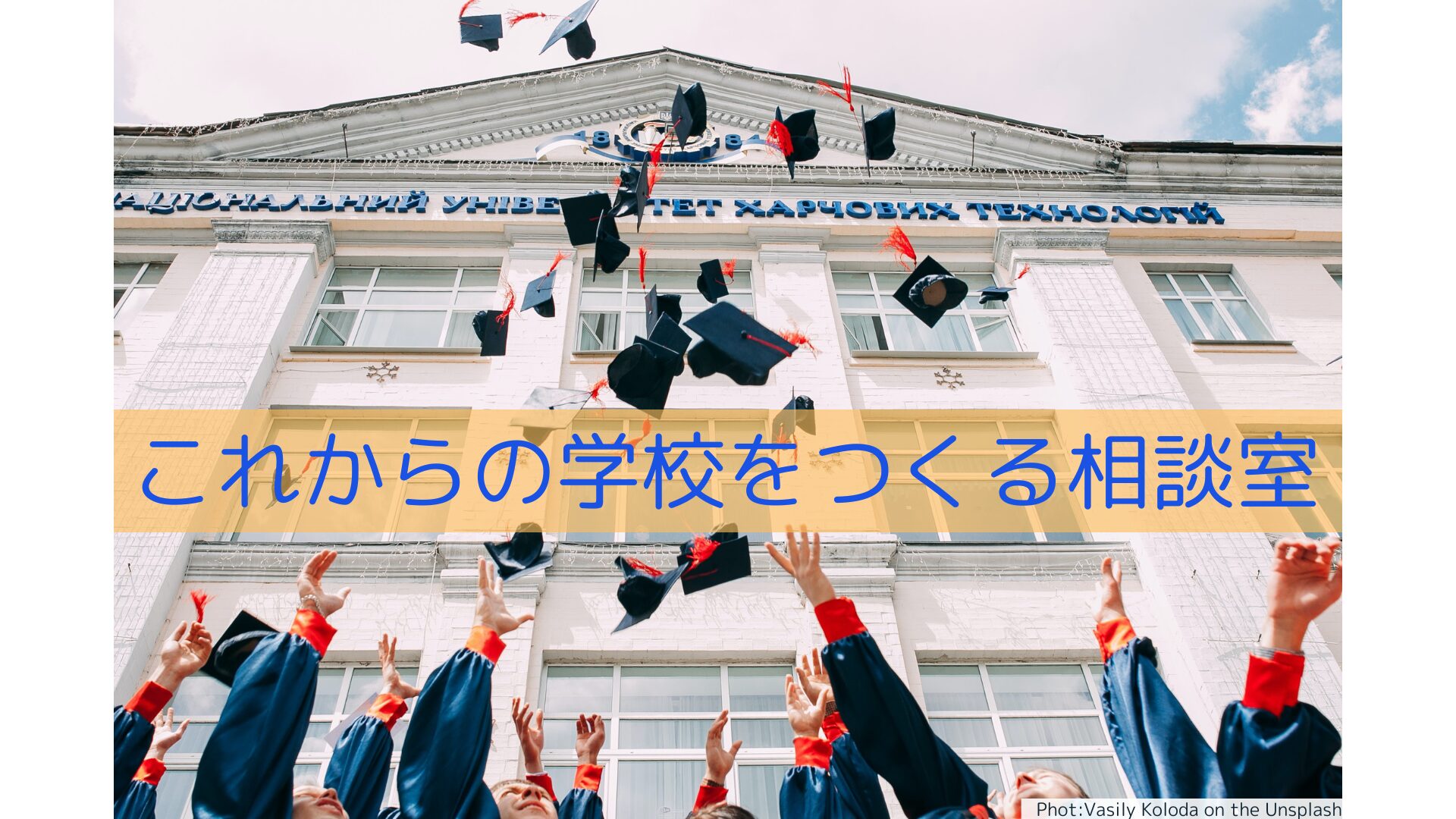






コメント