こんにちは
本ブログの管理者 とも@生き方カウンセラーです
初めて支援をしたり、支援することに慣れていないといった場合に、クライアントや相談者を怒らせたり、嫌な顔をさせてしまった経験はある方が多いと思います
この際に「問いかけ」の種類を意識することで、クライアントや相談者を怒らすのではなく、一緒に考えていく支援につながると考えます
「基本的な問いかけ」として、Edgar. H. Schein(以下、「Schein」とします)は、以下にある支援をする際の4つの「基本的な問いかけ」を示しました
1.純粋な問いかけ
2.診断的な問いかけ
3.対決的な問いかけ
4.プロセス思考型の問いかけ
これらの4つの「基本的な問いかけ」については、
相手を怒らせたり、支援関係をだめにしたり、その進行を遅らせたりする危険性は、純粋な問いかけから、診断的な問いかけ、さらに対決的な問いかけ、プロセス指向型の問いかけへと移行するにつれて増していく
クライアントの信頼を築き、喜んで影響を受けたいという態度を示してもらうために、支援者は「純粋な問いかけ」から始めるのが最もいい
と示しています
これらについて、例を踏まえて、お伝えします
※この記載は、「人を助けるとはどういうことか 本当の『協力関係』をつくる7つの法則」(エドガー・H・シャイン、訳 金井真弓、監訳 金井壽宏、2014年、英治出版株式会社)および、「問いかける技術 確かな人間関係と優れた組織を作る」(エドガー・H・シャイン、訳 原賀真紀子、監訳 金井壽宏、2014年、英治出版株式会社)を参考にしてます

この著書の中で、Scheinは、支援を求める人(相談者、クライアント)と支援者(カウンセラー)の立ち位置の違いについて示しています
・支援を求める人は、「一段低い位置に身を置く」
・支援者(カウンセラー)「一段高い位置に身を置く」
「このため、どんな支援関係も対等な状態にない。支援のプロセスで物事がうまくいかなくなる原因の大半は、当初から存在するこの不均衡を認めず、対処しないせい」としています

Scheinの考えと発想の土台として、「支援者側の無知」ということがあります
「支援する側が、親しいクライアントについてさえ知らないことがいっぱいあるのに、ましてや見知らぬ人の質問に、いきなり「答え」──つまり、内容面でのアドバイス──を勧告してしまう
内容(コンテント)に入る前に、まず、クライアントが何を求めているのかを知る、場合によってはともに考えるための過程(プロセス)のほうが大事である」
があります
また、支援者が選べる役割が3種類あるが、「初めのうちはプロセス・コンサルタントの役割を身につけることが重要」としています

Scheinは、「最初の問いかけは、『控えめな問いかけ』と呼ぶものでなければならない」としています。次の4つの問いかけ方を示しています
※「人を助けるとはどういうことか 本当の『協力関係』をつくる7つの法則」の中で出てくる「控えめな問いかけ」と「問いかける技術 確かな人間関係と優れた組織を作る」の中で出てくる「謙虚な問いかけ」は、いずれも原文において「Humble Inquiry」である。また、この2冊の中では、「控えめな問いかけ」と「謙虚な問いかけ」は、同じ意味として用いられているように読み取れます
そこで、本ブログにおいても、この2つは同じものとして考えます
1.純粋な問いかけ

この問いかけは、「クライアントの話だけに集中するもの」です
Scheinは、この「純粋な問いかけ」を「純然たる問いかけ」ともしています
Scheinは、「純粋な問いかけ」のプロセスの目的として、次のことを示しています
⚪︎クライアントの立場を確立し、自信を育てること
⚪︎クライアントが不安や情報、感情をさらけ出しても安全だと感じる状況を作ること
⚪︎その状況についてできるだけ多くの情報を集めること
⚪︎診断や行動計画のプロセスを通じてクライアントに関わること
【具体的な「純粋な問いかけ」の例】
《例1》
子供「先生〜」
先生「どうしたの?(純粋な問いかけ)」
子供「もう、どうしていいかわからない」
先生「どうしていいかわからなくなっちゃったんだね。何があったのかなぁ。(純粋な問いかけ)」
《例2》
保護者「先生、相談があるんです」
先生「相談と言いますと?(純粋な問いかけ)」
保護者「実は、子供とうまく話ができないんです」
先生「お子さんとうまく話ができないんですね
もう少し、具体的に教えてもらってもよろしいですか(純粋な問いかけ)?」
《例3》
先生A「どうしよう。。。」
先生B「心配なことでもあるの(純粋な問いかけ)?」
先生A「はい。。。でも、先生Bに言ってもしょうがないと思うんですけどね」
先生B「私に言ってもしょうがない、か。確かに、私に何ができるか分かりませんが、先生Aが、よろしければ、話をしてみませんか(純粋な問いかけ)?」
《例4》
地域の方「近くの公園の遊具で、大声を出している子供がいるのでやめさせてほしいので、今すぐに、この公園に来てくれませんか」
先生 「もう少し、詳しくお話を伺ってもよろしいですか(純粋な問いかけ)?」
「純粋な問いかけ」の決まった型はありません
しかし、共通していることがあります
それは
⚪︎自分が知らないということを積極的に認めていること
⚪︎支援者がクライアントを受け入れていること・興味を持っていること
⚪︎クライアントの現在置かれている状況についてどう思っているのかを知りたいということ
⚪︎初めのうちは、起きている事柄だけに集中して話を聴くこと
です
このような姿勢で、支援者が対応することで、クライアントは快適に感じる方法で支援者に接することができるようになります
さらに、クライアントは、支援者に相談することにより、立ち位置が支援者よりも一段階下になります
その結果、クライアントは、相談を通して支援者に依存しがちになります
しかし、傾聴をしていくことにより、
「クライアントが重要なことを知っているから、それを私に教えてください」
という、クライアントの立ち位置が元に戻っていきます
その結果、クライアントの立場を確立していきます
支援者は、クラインアントにさらなる情報を求めることで、次の3つの重要なことを成し遂げています
1 何か重要なことを知っているという役割を与えて、クライアントの立場を確立すること
2 その状況への関心や思い入れを伝えて、一時的なものであるにせよ、人間関係を築く意欲を高めること
3 重要な情報を得ること
このように、「純粋な問いかけ」をしていくことで、支援者とクライアントが相互に支えながら、相談が進行していきます
さらに、クライアントに情報を提供してもらいたい場合には、「診断的な問いかけ」に段階を進めていく方法もあります
2.診断的な問いかけ

この問いかけは、「感情や、原因分析、行動の代替案を引き出すもの」です
「診断的な問いかけ」のプロセスの目的は、
クライアントの心理作用を促し、クライアントの自己認識(自分自身の行動を診断する力)を助けてくれること
と考えています
「診断的な問いかけ」をすることで支援者はクライアントが話そうとしたものと違う話題にわざと焦点を当てることによって、相手の心理(思考)プロセスに影響を与え始めます
→クライアントが最初に聞いてきたことに答えるかわりに、こちらから質問するということは、支援者がその会話の方向性を決める立場(会話の主導権を握るという行為)になります
このような依頼者の思考プロセスに影響を与えるような問いかけというのは、支援者がなにに診断の焦点を当てるかによって、次の4つに分類することができます
感情と反応──これはクライアントが述べた出来事や、認識された問題に対してクライアント自身がどう感じ、どう反応したかに焦点を当てるもの
原因と動機──質問して、原因についての仮説を立てれば、クライアントは支援を求めようとする動機に焦点を当てさせられ、話しているうちに、そんな状況になった理由を発見する
実行に移した行動、または検討中の行動──この問いかけの形はクライアントに、自分たちや話に登場する人々がしたことや、しようと考えていること、将来に実行しようと計画していることに焦点を当てさせる
体系的(システミック)な質問──クライアントにとっても支援者にとっても、クライアントの話に登場する人たちの反応を理解することが重要だと考えて、周囲の人々がどう思っているのか、どのような反応をしているのかと、状況の全体像を把握するためにする質問
【具体的な「診断的な問いかけ」の例】
《例1:感情と反応》
子供「実は、昨日、友達と言い合いになり、今日も話すことができなかったんです」
先生「今日も話すことができなかったんだ。このことをどう感じているの(感情と反応)?」
《例2:原因と動機》
保護者
「子供が試験が近いのに、全く勉強している様子がなくて
昨日も怒ってしまったんです
そしたら、子供はイライラした様子で、自分の部屋にこもってしまったんです。食事はするのですが、一言も喋らず、食べ終わったら自分の部屋に入ってしまって
さすがに、今日の学校には行くだろうと思ったら、今日も部屋から出てこなくて」
先生
「なるほど
お子さんが試験が近いのに勉強していなくて、お母さんが怒ってしまったんですね
それから、部屋にこもっていると」
保護者
「はい
どうしたらいいのかわからなくなってしまって。。。」
先生
「どうしていいか分からなくなってしまって怒ってしまったのは、どんなことを考えてですかねー(原因と動機)?」
《例3:実行に移した行動、または検討中の行動》
先生A
「今日、学級費を回収したんですよ」
先生B
「うん、うん」
先生A
「そしたら、子供たちが私の周りに集まってきて、一気に集金袋を渡してくれました
とりあえず、渡してくれた集金袋はその場で回収し、職員室で金額を確認していたんです
すると、Cさんの集金袋がなかったんです
なので、Cさんに、集金袋を出したか確認したら、『出しました』と言われてしまって」
先生B
「なるほど
学級費を回収し、確認したらCさんのだけがなかったんですね」
先生A
「そうなんです
何度も確認したんですが、やはり、Cさんのだけがなかったんです
私が落としてしまったのかなぁ。それとも、Cさんが嘘ついているのかなぁ。。。」
先生B
「自分が落としたか、Cさんが嘘ついているかもと考えている状況なのですね
この先、どのようにしていこうと考えていらっしゃるんですか(検討中の行動)?」
《例4:体系的(システミック)な質問》
地域の方
「最近、私の家の裏にある公園で、子供たちが、よく大声を出して遊んでいるんです
公園なので、子供たちが声を出すのはわかるんです
しかし、最近は、『ぎゃー』とか、『わー』とかいう声がとても大きくて、昼寝をすることもできないんです」
先生
「なるほど
最近、ご自宅の裏にある公園で、子供たちの大きな声が気になり、お昼寝することもできない程なんですね
最近ということは、その以前は、子供たちは、大きな声を出していなかったのですか?」
地域の方
「分かりません
公園なので、大きな声を出していたかもしれません
私が、最近、身体を壊し、仕事をやめ、昼間も家にいることが多くなったので、気づいたのかもしれません」
先生
「最近、お身体を壊してしまい、昼間も家にいることが多くなった
なので、家でお昼寝をしようと思っても、子供たちの声がうるさくて眠れないということなんですね」
地域の方
「そうなんです
起きていると、身体がしんどくなり、昼寝をしないと、夜まで体力が持たなくて。。。」
先生
「もし、このようなことを子供たちに、ご自身で説明されたら、子供たちはどうすると思われますか(体系的(システミック)な質問)」
これら4つに分類できる「診断的な問いかけ」は、
いずれも相手の思考のプロセスをある方向に導き、その人自身に「気づき」があるようにする
ものです
しかし、あくまでも問いかけであって、
特に何かの解決策をほのめかすわけではありません
クライアントの現在の問題の実質的な内容に影響するが、本人が思いつきもしなかったような発想を会話に持ち込むのが、「対決的な問いかけ」です
3.対決的な問いかけ

この問いかけは、「現状について支援者自身の見解をもたらすもの」です
この「対決的な問いかけ」を用いるときは、注意が必要です
それは、この「対決的な問いかけ」は
支援者はクライアントが思いつかなかったような提案をしたり意見を述べたりする
ため、
クライアントが、一段低い位置にいることをさらに感じる
ことがあるからです
そうした介入のしかたは専門家や医師の役割を強く帯びるので、
有効なコミュニケーションを可能にするだけの信頼や公平さが、充分に関係の中で育ったと支援者が感じた場合
に用います
「対決的な問いかけ」は、「診断的な問いかけ」と同じ分類に当てはめて考えることができます
【具体的な「対決的な問いかけ」の例】
《例1:感情と反応》(参考「診断的な質問」 例1)
子供「実は、昨日、友達と言い合いになり、今日も話すことができなかったんです」
先生「今日も話すことができなかったのは、悲しかったの(感情と反応)?」
《例2:原因と動機》(参考「診断的な質問」 例2)
保護者
「子供が試験が近いのに、全く勉強している様子がなくて
昨日も怒ってしまったんです
そしたら、子供はイライラした様子で、自分の部屋にこもってしまったんです
食事はするのですが、一言も喋らず、食べ終わったら自分の部屋に入ってしまって
さすがに、今日の学校には行くだろうと思ったら、今日も部屋から出てこなくて」
先生
「なるほど
お子さんが試験が近いのに勉強していなくて、お母さんが怒ってしまったんですね
それから、部屋にこもっていると」
保護者
「はい
どうしたらいいのかわからなくなってしまって。。。」
先生
「どうしていいか分からなくて怒ってしまったのは、お母さんがお子様の将来を心配されてのことだったのですかね(原因と動機)?」
《例3:実行に移した行動、または検討中の行動》(参考「診断的な質問」 例3)
先生A「今日、学級費を回収したんですよ」
先生B「うん、うん」
先生A
「そしたら、子供たちが私の周りに集まってきて、一気に集金袋を渡してくれました
とりあえず、渡してくれた集金袋はその場で回収し、職員室で金額を確認していたんです
すると、Cさんの集金袋がなかったんです
なので、Cさんに、集金袋を出したか確認したら、『出しました』と言われてしまって」
先生B
「なるほど
学級費を回収し、確認したらCさんのだけがなかったんですね」
先生A
「そうなんです
何度も確認したんですが、やはり、Cさんのだけがなかったんです
私が落としてしまったのかなぁ。それとも、Cさんが嘘ついているのかなぁ。。。」
先生B
「自分が落としたか、Cさんが嘘ついているかもと考えている状況なのですね
もう一度、Cさんに詳細を確認してみますか(検討中の行動)?」
《例4:体系的(システミック)な質問》(参考「診断的な質問」 例4)
地域の方
「最近、私の家の裏にある公園で、子供たちが、よく大声を出して遊んでいるんです
公園なので、子供たちが声を出すのはわかるんです
しかし、最近は、『ぎゃー』とか、『わー』とかいう声がとても大きくて、昼寝をすることもできないんです」
先生
「なるほど
最近、ご自宅の裏にある公園で、子供たちの大きな声が気になり、お昼寝することもできない程なんですね
最近ということは、その以前は、子供たちは、大きな声を出していなかったのですか?」
地域の方
「分かりません
公園なので、大きな声を出していたかもしれません
私が、最近、身体を壊し、仕事をやめ、昼間も家にいることが多くなったので、気づいたのかもしれません」
先生
「最近、お身体を壊してしまい、昼間も家にいることが多くなった
なので、家でお昼寝をしようと思っても、子供たちの声がうるさくて眠れないということなんですね」
地域の方
「そうなんです
起きていると、身体がしんどくなり、昼寝をしないと、夜まで体力が持たなくて。。。」
先生
「もし、このようなことを子供たちに、ご自身で説明したら大声を出さなくなりますかね(体系的(システミック)な質問)」
「対決的な問いかけ」の最大の危険は、
クライアントの状況を示す新たな情報を得られなくなること
です
というのも、今やクライアントは支援者に紹介された新しい概念に対処するのが精いっぱいで、思考や記憶を語り続ける余裕はなくなってしまいます
「対決的な問いかけ」をする前に、
なぜ、それを聞きたいのかを自分自身に問うこと
が大切です
「私には、解決策が見えているので、自分が正しいことを証明してみせようと思っている」
のであれば、
「自分が言いたいことを言う」
という発想に、支援者が流されてしまっているので、その結果、相手が自己弁護を始めても不思議がありません
4.プロセス思考型の問いかけ

この問いかけは、「クライアントに支援者との即座の相互関係に専念させるもの」です
この「プロセス思考型の問いかけ」の目的は
クライアントと支援者の間には相互関係が働いており、分析できるものだ、という事実をクライアントに意識させること
です
つまり、
クライアントの状況や内容から、その場で起きているクライアントと支援者との相互関係に視点を移す
時(良好な関係を築きたいと思っている相手との会話が少しおかしな方向へずれてしまった時等)に、この「プロセス思考型の問いかけ」を用います
この「プロセス指向型の問いかけ」は、ほかの種類の問いかけとも結びつけられます
具体的な例を見てみましょう。
【具体的な「プロセス思考型の問いかけ」の例】
《例1 純粋にプロセスについて問いかける》
「どうなさいましたか」
「立ち入った質問をしてしまったでしょうか」
《例2 診断的にプロセスについて問いかける》
「私に、このことを話そうと思ったのは、どんなことを考えてでしょうか」
「他に、どのようなことをお聞きしたらいいでしょうか」
《例3 対決的にプロセスについて問いかける》
「私の質問があなたの感情を刺激してしまったのでしょうか」
「何か、私が気に障ることを言いましたか」
このような問いかけをすると、両者の関係が焦点として浮上し、互いの目的が合致しているかどうを判断する機会が持てます
まとめ
「支援をする際に、相談者と失敗しない基本的な4つの問いかけ方」についてまとめます
1.純粋な問いかけ
2.診断的な問いかけ
3.対決的な問いかけ
4.プロセス思考型の問いかけ
友達や仲間との関係、授業や学級づくり、学校づくりを解決すること方法の1つとして、話をすること・相談することがあります
本ブログでは、進路や生き方の悩みに対しての相談を受け付けています

相談をご希望の方は、「相談の申し込み」をご利用ください。
最後まで、よんでいただき、ありがとうございました
また、この記事等に関してなど、何かありましたら、や「お問い合わせ」をご利用下さい。
すぐに返せないこともあると思いますが、必ず返信いたします
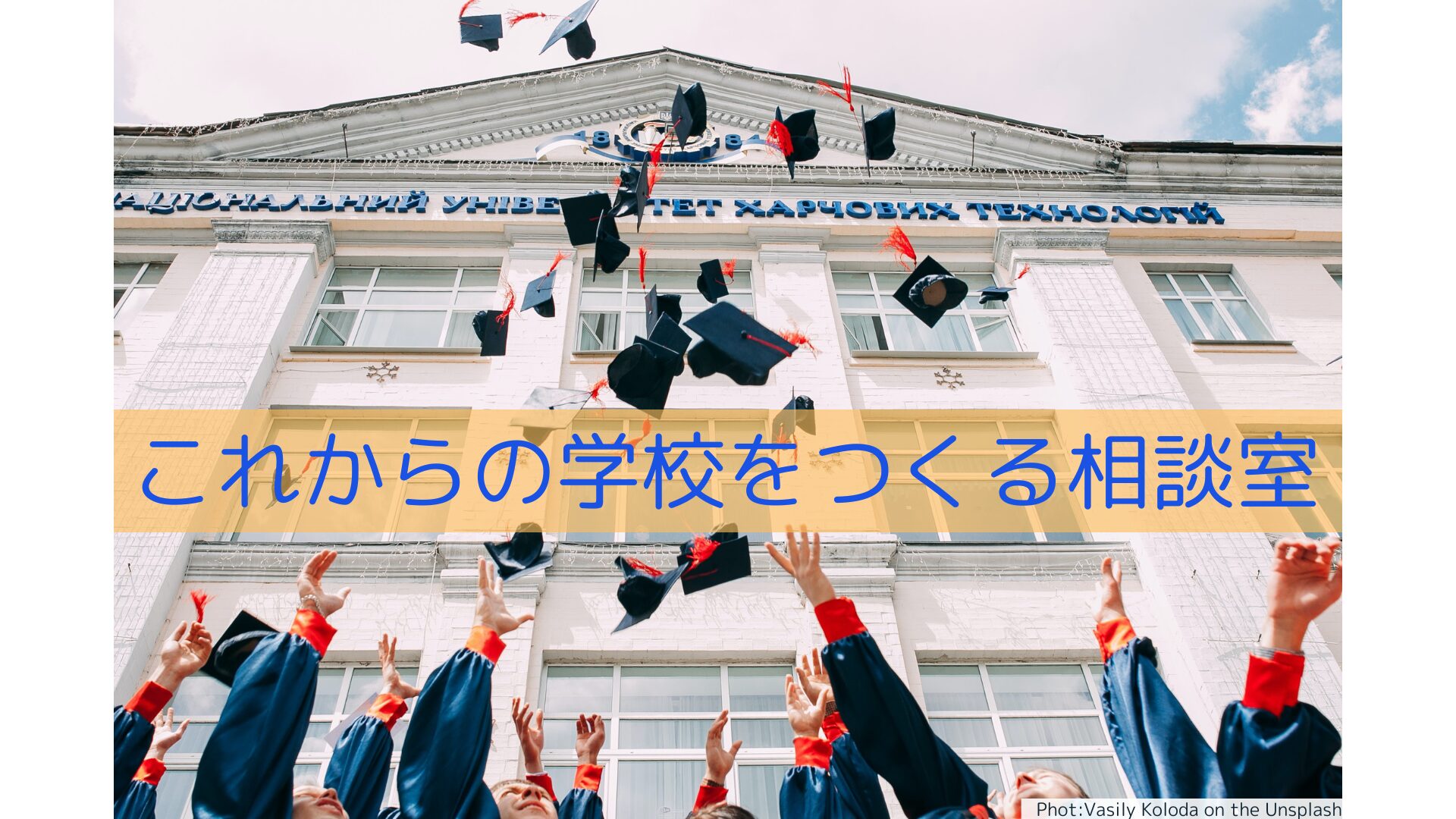






コメント